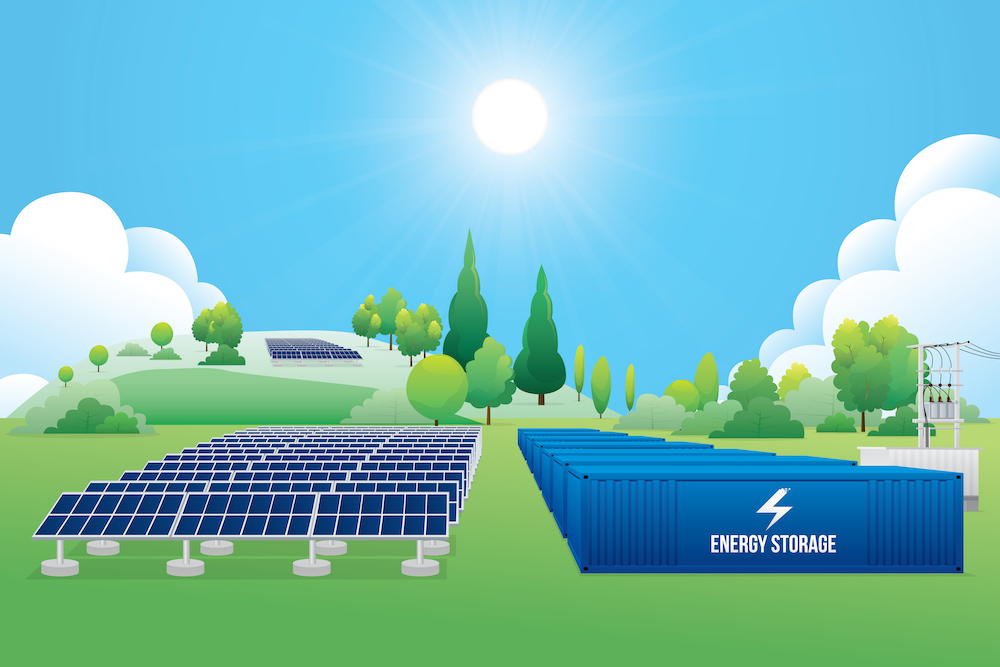社会全体で資源を最大限に活用するための省エネが推進されていますが、そこで企業や公共団体で導入されているのがESCO事業です。
ESCO(エスコ)はエネルギー・サービス・カンパニーの頭文字から名付けられています。
事業者は、クライアントのビルや工場でエネルギーの削減に必要なサービスを提供することで、削減できた光熱水費からエネルギーの削減でかかった経費や金利などをあわせたサービス料を徴収します。
目次
事業者が金融機関とシェアード・セイビング契約を結んで資金調達をする
省エネ性能に優れた設備を導入したり、建物の改修を行うとなれば企業や公共団体にとっては大きな負担です。
でも、省エネができたあとに削減分から料金を支払うとなれば、初期費用を用意する必要ありません。
では、必要となる資金はどうやって捻出するのかというと、エスコシステムズなどの事業者が金融機関とシェアード・セイビング契約を結んで資金調達をします。
そしてサービス料から必要な文を回収していきます。
金融機関から企業や公共団体が融資を受けるときには、審査に通らないこともありますが、金融機関が相手にするのは事業者なので審査のことを心配することはないし、返済についてもリスクを負うことはないです。
そうして支払うサービス料ですが、削減した分をそっくりそのまま事業者に回すのではなく、一部は残るのでそれが利益としてクライアントに入ってきます。
しかもサービス料の支払いは、契約期間だけのことです。
契約期間が終了すればサービス料は必要なくなるので、クライアントは削減分をすべて自分のものにできます。
契約期間について
では、契約期間はどの程度になるのかというと、多くの場合には十数年という長期契約です。
かなり長くはなりますが、長期の返済をしていくことで1回あたりのサービス料の支払い負担が減らせるので資金にそれほど余裕がない企業や公共団体でも導入しやすいです。
もともと何もしなければ、多額の光熱水費を支払い続けていたわけですから、削減分からサービス料を支払うとしても損をするわけではありません。
むしろ、初期費用を負担せずに省エネができるのは大きな魅力です。
他にもESCO事業の導入をすることには意味があります。
企業や公共団体には、環境問題に対して積極的に取り組む責任が求められます。
利益を増大させることが、そういった責任を果たすことに繋がるとなれば一石二鳥です。
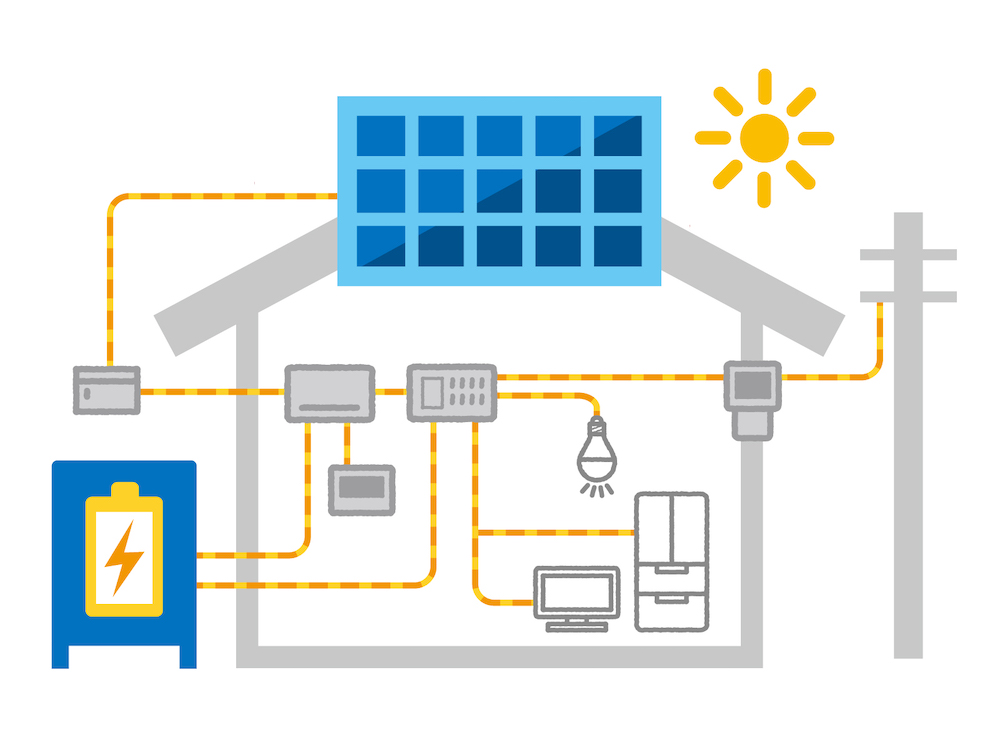
導入後に達成できる省エネ効果を事業者が保証している
ESCO事業で特徴的と言えることは、導入後に達成できる省エネ効果を、事業者が保証していることです。
サービス料金と一定の利益に相当する分の光熱水費を絶対に削減できると最初に約束しています。
もし、導入後に、その約束を果たせず思ったよりも省エネ効果が出ずに損失が生じたら、その分を事業者が補填することになっています。
ただし、普通の状態では想定できないインフレやデフレ、気象変動などが起きて目標を達成できないときには、その影響を受けた分は省エネ効果の保証からは外れます。
エネルギーの削減をするための設備投資や改修というのは、ESCO事業を導入しなくても可能です。
でも省エネ効果を増やすためには、設備投資や改修をしたあとに計測と検証をするも大事です。
いくら設備を投資や改修をしたとしても、時間の経過とともに劣化していき省エネ効果は低くなってしまいます。
企業や公共団体は専門的な知識や技術を持っているわけではないので、そういう変化を完全に把握することは難しいです。
でもESCO事業では事業者が包括的なサービスを提供しており、そういった計測や検証も仕事のうちです。
契約期間中は維持管理を徹底して行うので、長期的な省エネ効果は事業者の手を借りない場合と比べて大きな差が生じます。
事業者が途中で倒産してしまう可能性も否定できない
ここまでは主にメリットについて触れてきましたが、不安材料もあります。
たとえば長期的な契約をしているので、事業者が途中で倒産してしまう可能性も否定できません。
大抵の場合、導入した設備は事業者あるいはリース業者のものを借りている形になっているので、所有権が誰に渡るのかわかりません。
そこで契約をするときには、最初の事業者が倒産したときには次にサービスを提供できるだけの力を持った事業者が引き継ぐこと、もしそれが困難なときには設備の所有権をクライアントに譲渡することなどを盛り込むことで、リスクを回避できます。
そして、ESCO事業を進めていくときに発生する問題もあります。
事業者が包括的にサービスを提供するときには、クライアントは契約の条件に沿った経営をしなければいけません。
もし、何らかの事情で契約外の改修工事をするときには、そのことで想定していた省エネ効果が達成できないことがあります。
そうなれば、契約の内容を見直さなければならず、クライアントの負担が増します。
まとめ
それから、クライアントと事業者の連携も問題になります。
計測・検証をしながら保守管理をしていく中で、ある程度は建物を管理するクライアントに作業を任せる部分もあります。
そうなると、全てのデータを事業者が把握できなかったり、サポートが思うようにできなかったりします。
クライアントと事業者との間で、情報をしっかりと共有できる体制を整えなければいけません。
最終更新日 2025年5月15日 by ewbcjp